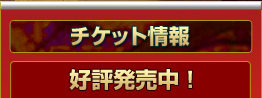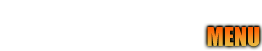「ノートルダム・ド・パリ」日本公演開幕には、
作曲家のリシャール・コッシアンテ氏がイタリアから駆けつけました。
そこで、フランス・ミュージカル研究の第一人者、
渡辺 諒教授による、コッシアンテ氏へのインタビューが行われました。
-

2月27日(水)の『ノートルダム・ド・パリ』初日を前に、前日の午後、作曲を担当したリシャール・コッシアンテ氏に、短い時間ではあったがインタビューすることができた。夫人共々、初来日とのこと。以下は、その概要である。
インタビューは、彼が生まれたベトナム、サイゴンの思い出からはじまったが、「素晴らしい時代」だったと一言。ヨーロッパと切り離されたアジアの思い出は、彼の音楽活動に陰に陽に影響を与えており、『ノートルダム・ド・パリ』に直接その影響をみることはできないが、他の作品にその痕跡が見られるという。
彼は(父はイタリア人、母はフランス人ということもあり)つねづね「自分はフランス人でありイタリア人」「ふたつの国籍を持っている」といっているが、幼年時代の家族の言語はフランス語であり、イタリア語は、11歳でローマに戻ってからはじめて学んだとのこと。両者の関係はどうなっているのか、そこに対立;や衝突はないのか、というきわめて素朴な?筆者の質問に、フランス語とイタリア語はもともとラテン語からきており、従兄弟同士のようなもの。ただし、フランスの歌手はとてもフランス的だし、イタリアの歌手はとてもイタリア的であることも確か。自分はいわばその間におり、むしろ、両者の差異を楽しんでいる。いや、フランス語、イタリア語にとどまらない、さまざまな言語の多様性を生きることが自分の差異=個性である、と彼は言う。いずれにせよ、音楽であれなんであれ、型にはまった表現、「紋切り型(cliché)」からいつも逃れたいと思っている、というのがコッシアンテ氏の信条のようだ。
言語の多様性からパフォーマンスの多様性へ。彼自身、作者であり作曲家であり演奏家であることはよく知られているが、たとえば他の歌手たちとのコラボ作品も多い。あるときはフランス語で唄い、またあるときはイタリア語、スペイン語、英語でといった具合だ。それはなぜなのか、そのような試みの目的は、という筆者の質問に、「試み」ではない、すでに実践している以上「キャリア」だという夫人からの鋭い指摘。異なる国の異なる言語を話すアーティストたちと一緒に唄いたい。翻訳不可能な、各言語の微妙なニュアンスを生かすにはそれぞれの言語で唄うしかない。多様性を生きるというよりは、むしろ多様な差異化への欲求がたえず彼を駆り立てているようだ。
ついで、彼自身の「ミュージカル(フランス語で comédie musicale という)」について話を移そうとすると、『ノートルダム・ド・パリ』はミュージカルではないと現下に否定された。いわゆるミュージカルとは別のものを作りたかった、別の「ティポロジー」(分類)が必要だ、と。彼の言をかりれば「スペクタクル・ミュージカル」。自分が目指したのはクラシックとロックとの混淆であり、われわれの世紀に属する「民衆オペラ(opéra poplulaire)」(「オペラ・ポポラーレ」という夫人からの指摘)にほかならない。いずれにせよ、「ロック・オペラ」『スターマニア』の作詞家プラモンドンとの共同作業は、コッシアンテ氏にとって新たな挑戦、新たな転換点になったようだ。あたらしいスタイルの「ロック・オペラ」をつくりあげること(ちなみに、イタリア語バージョンははっきりとオペラと銘打たれている)。ロイド=ウェバーの「ロック・オペラ」(『ジーザス』)との違いをただすと、自分の音楽はロックにとどまるものではない。たとえば、同じ打楽器でも、狭義のリズムを刻む「打楽器(batterie)」ではなく、広義の「打楽器(percussions)」を使用するという。現在と過去、時間的なものと時間を越えたものを混淆することこそ、あたらしい「スペクタクル・ミュージカル」の特質であるからだ。
では、プラモンドンが「異邦人(étrangers)」というテーマにこだわるように、コッシアンテ氏自身もそうなのかという筆者の問いに、なるほど「サン・パピエ」の問題はアクチュアルな問題であり、『ノートル=ダム・ド・パリ』は愛の物語であると同時に社会的な物語であるのは事実。異邦人(外国人であれ移民であれマイノリティーであれ)の問題は常に存在する。ヨーロッパはいまや簡単に行き来することができ、あらゆる国籍の人間で溢れている。自分はたえず旅し、他の人々とたがいに混じりあおうとしているが、たしかに容易ではない。
ところで、『ノートルダム・ド・パリ』に続くコッシアンテ氏の「スペクタクル・ミュージカル」は『星の王子さま』。なぜ Petit Princeなのかといえば、『星の王子さま』は一種のバイブルであり、フォンテーヌの『寓話』のような子供向けの作品であると同時に批評的な作品であるから。易しさと複雑さがそのキーワードだという。なぜ複雑かといえば、たとえば「バオバブの木」はファシズムの象徴とみなされるからだ。サン=テグジュペリによって描かれた素描が最初にあった以上、むしろ「見えるものと見えないものの物語」という側面もあるのでは、という筆者のコメントに、「魂と心の物語」ということばが間髪入れず返ってきた。星の王子さまは、サン=テクジュペリその人にほかならない、と。
ついで2007年に『ジュリエットとロミオ』が上演されたが、ヴェローナには「ロミオとジュリエット」というレストランと「ジュリエットとロミオ」というホテルがあるという。なによりも、シェイクスピアの作品そのものがすでに翻案であり、もとはイタリア(バンデッロの『ロミオとジュリエッタ』1554)。ロミジュリが、イタリア発であることを強調したかったのだという。とすれば、コッシアンテ氏の作品タイトルが『ロミオとジュリエット』ではなく『ジュリエットとロミオ』であるのは、ひとえにイタリア愛?のなせるわざなのだろうか。
ともあれ、『ノートルダム・ド・パリ』以降のフランスの「スペクタクル・ミュージカル」についてその感想を聞くと、『ノートルダム・ド・パリ』が大成功したために、みんなその制作システムや音楽・演出スタイルを真似しはじめたが、おしなべて成功とは言い難い、と辛口のコメント。音楽がロックにかたより、かつ商業主義に走っているというのがその真意のようだ。それだけに「スペクタクル・ミュージカル」というネーミングに相当の思い入れがあることは容易に理解されよう。
最後に日本のミュージカル事情について少し説明すると(ミュージカルはずいぶん日本の土壌に定着したが、外国作品の翻訳・翻案上演が多く、オリジナルな作品は少ない)、韓国も同じだろう、という返事。いまは模倣・同化の時期だろう、オリジナルな作品が生まれるには時間が必要だ。たしかに。しかしフランスの歴史と日本のそれを比べたとき、彼我の距離はいかんともしがたい。すくなくとも、『ノートル=ダム』以降、オリジナル作品を次々に生み出し、世界に向けて発信し続けているフランスに対し、日本の現況はどうだろう? 映画だって偉大な監督を生み出しているではないか、という彼の言葉をどこまで素直に受け取っていいものやら、すこし複雑な気持ちになってしまった。
音楽に言葉はいらない。日本の観客へのメッセージを一言求めると、「大いなる感情・感動 (grande émotion)」という言葉が返ってきた。 5日間しか日本での滞在期間がないという。インタビューは、「また来ます」という夫人の言葉で締めくくられた。